紀州の和菓子と文化を考える会11月学習会開催
2025年11月12日 17時45分
歴史・文化
社会
紀州の和菓子と文化を考える会の11月の学習会が、このほど(11月9日)、和歌山市で開かれ、和菓子文化の継承について考え、交流を深めました。

学習会では、まず、御坊市在住で、市の文化財保護審議会委員などを務める大谷春雄(おおたに・はるお)さんが、「日本文化における和菓子文化の位置付け~和菓子文化の伝承意義の再考察~」と題して講演しました。
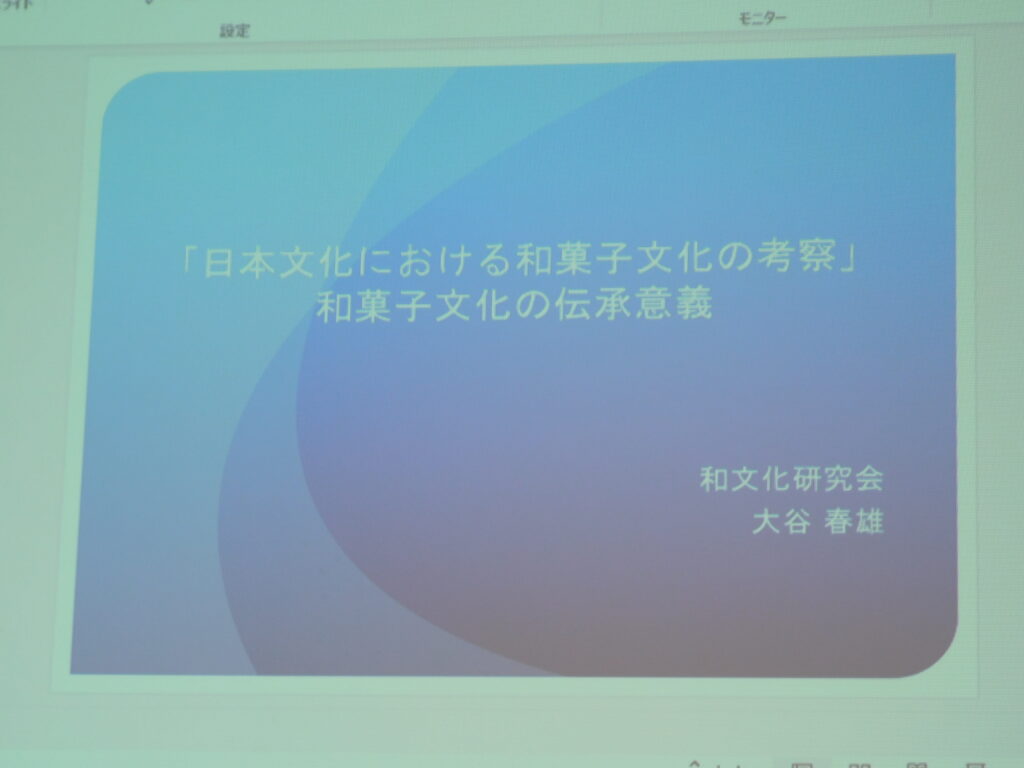
この中で大谷さんは「和菓子文化が、これから残っていくためには、健康志向であることと、製造の技術を継承していくことが大事」と述べた上で、「本物の和菓子を食べることが、大人にとっても、子どもたちにとっても、和菓子文化の継承につながるのではないか」と語りました。
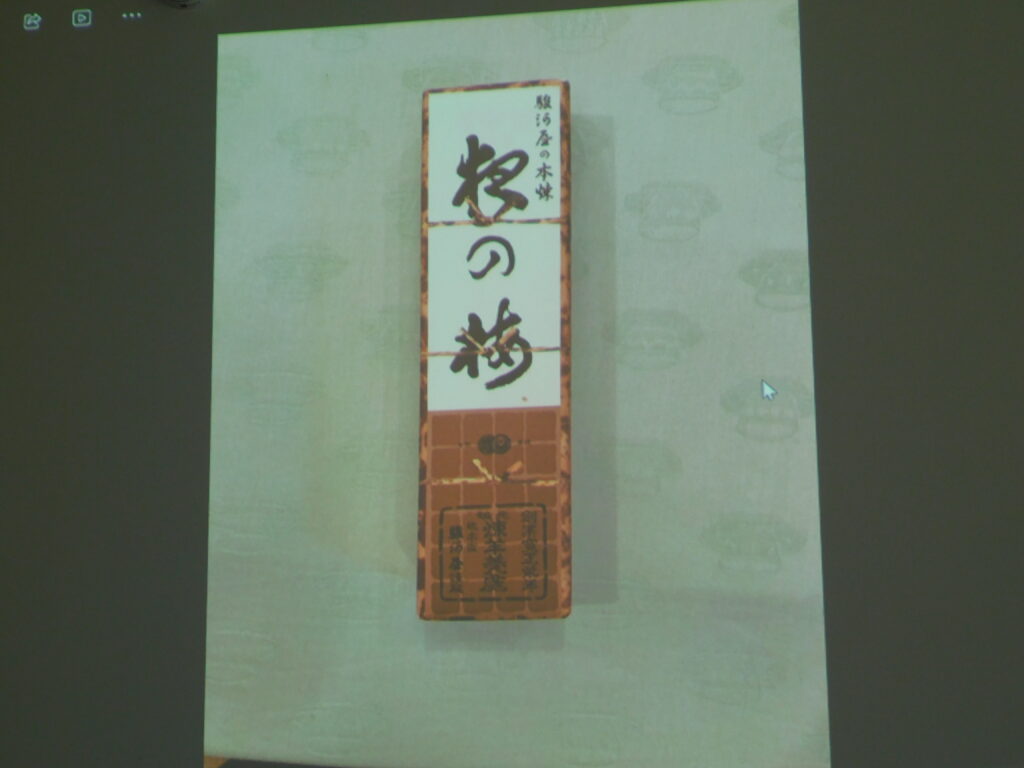
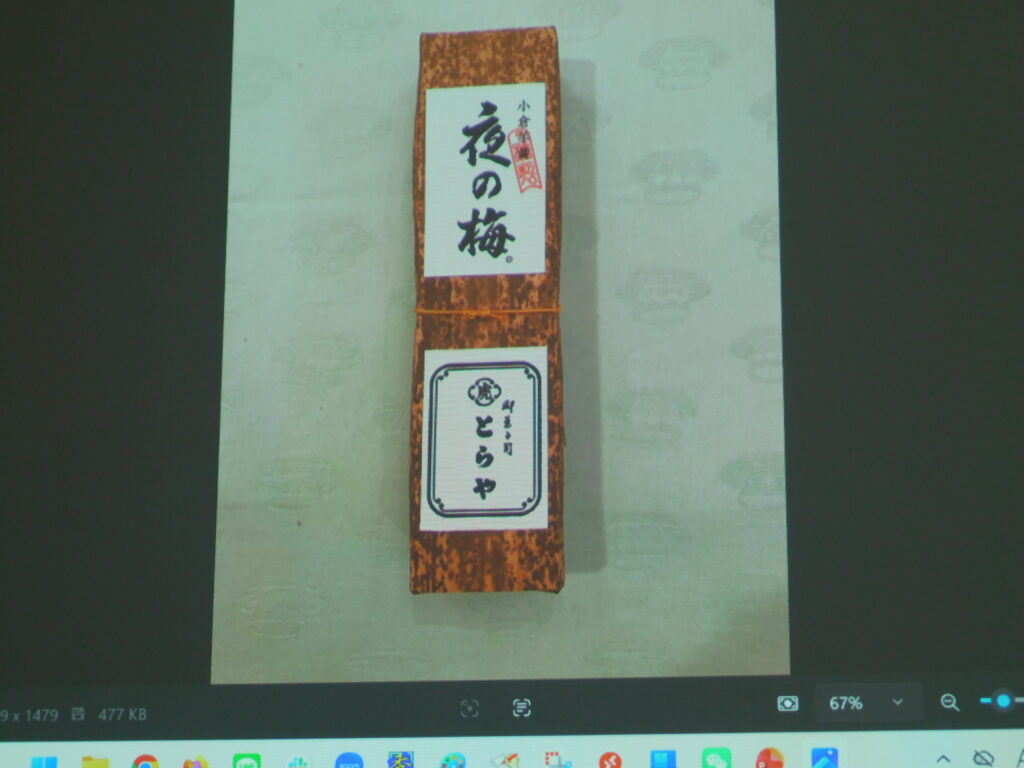
大谷さんは、「和菓子は、家族が買ってくる。一人で和菓子屋へ行く子どもはいなくて、コンビニで置いている和菓子も限られている。深みのある羊羹を並べると、子どもの世代も美味しく食べる。本当に美味しい物の縁が繋がれば、和菓子が普及していくのではないか」と述べました。

紀州の和菓子と文化を考える会の鈴木裕範(すずき・ひろのり)会長は、「和菓子を知りたければ、和菓子屋へ行くこと。店のご主人や奥さんと話をして、そこに生まれるコミュニティが継続して行く。良いお菓子を作っても大きな儲けにはならない。それでも作ってくれるのは、それを期待している人がいる、喜んでくれる人がいるから。だから頑張れる」と話しました。
会では、御坊市の「御菓子司(おかしつかさ)有田屋(ありだや)」の季節の特製菓子「銀杏(ぎんなん)」をいただきました。次の学習会は、来年春を予定しています。

